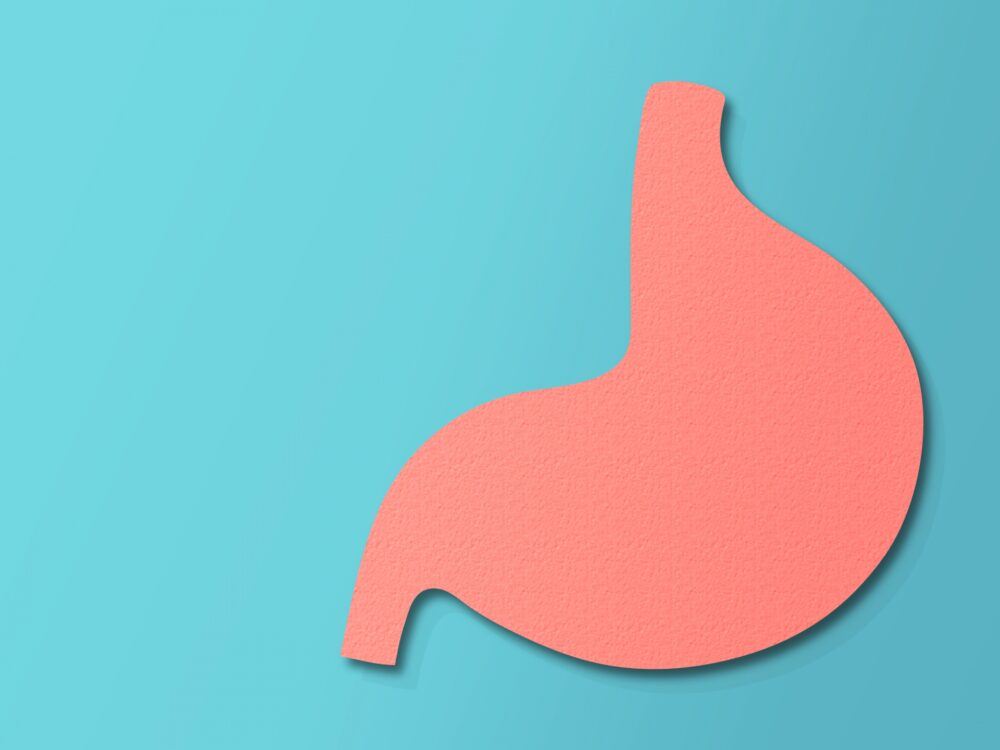胃がんの手術を告げられたら。基本知識と最新の治療法

「胃がんの手術が必要です」という言葉を医師から告げられたとき、多くの方は不安や緊張を感じることでしょう。
「おなかを切るのは怖い」「手術のあと、今まで通りに食事ができるのだろうか」「仕事や家事に戻れるのか」といった悩みは、患者様だけでなく、支えるご家族にとっても共通のものです。
胃がんの治療において、手術はがんを完全に取り除き、「根治(こんち)」を目指すための最も重要な柱となります。
医療技術の進歩により、現代の手術は以前に比べて格段に進化しました。体への負担を最小限に抑える方法や、最新のロボットを用いた精密な技術、そして手術前後の生活を支える栄養指導など、多方面から患者様を支える体制が整っています。
このコラムでは、胃がん手術の基礎知識から、最新の術式、入院前にできる準備、そして術後の生活で知っておきたい工夫まで、一歩先を見通すための情報を詳しく解説します。
これから始まる治療の道のりを、少しでも穏やかな気持ちで歩んでいただくための手助けになれば幸いです。
胃がん手術の基本知識

手術が検討される病期(ステージ)
胃がんの治療方針を決定する上で、最も重要となる指標が「病期(ステージ)」です。
ステージは、がんが胃の壁のどのくらいの深さまで入り込んでいるか(浸潤:しんじゅん)、そして周囲のリンパ節や離れた臓器(肝臓や肺、腹膜など)への転移があるかどうかによって、Ⅰ期からⅣ期まで分類されます。
一般的に手術が検討されるのは、がんが胃の周辺にとどまっており、手術によってすべて取りきることが可能であると判断された場合です。
具体的には、ステージⅠ期からⅢ期までが主な対象となります。
早期がんであれば内視鏡による切除も検討されますが、がんが少し深い層に達していたり、周辺のリンパ節に転移の可能性がある場合は、外科的な手術による広範囲な切除が必要となります。
一方で、ステージⅣ期のように、がん細胞が血液やリンパ液の流れに乗って、胃から遠く離れた臓器(遠隔転移)に広がっている場合は、手術だけでがんをすべて取り除くことが難しいため、基本的には「化学療法(抗がん剤治療)」が治療の中心となります。
しかし、近年では抗がん剤の進歩により、化学療法でがんを小さくしたあとに手術を行う(コンバージョン手術)という選択肢も生まれています。
このように、手術の適応は患者様一人ひとりの詳細な検査結果に基づき、慎重に決めていくことになります。
手術の目的
胃がんにおける手術の最大の目的は、がん細胞を体の中から確実に取り除き、再発を防いで命を守ることにあります。
外科手術で行われるのは、単に「胃を切る」ことだけではありません。実は、それと同じくらい重要なのが「リンパ節郭清(りんぱせつかくせい)」という処置です。
がんは目に見える腫瘍の周りにあるリンパ節という小さな組織を通って、他の場所へ広がろうとします。
手術では、がんが転移している可能性がある周辺のリンパ節を、脂肪組織とともに一塊(ひとかたまり)として切除します。
これにより、目に見えないレベルの小さながん細胞まで取り除くことを目指します。
また、もう一つの重要な目的は、食事の通り道を再建し、消化吸収機能を維持することです。
がんによって胃の出口や入り口が狭くなっている場合、それらを取り除き、残った胃と腸、あるいは食道と小腸をつなぎ合わせることで、再び口から食事を摂れるように整えます。
手術は決して「奪う」ためのものではなく、これから先の健やかな生活を「取り戻す」ための前向きな選択であると言えます。
主な手術方法と最新技術

胃を切る範囲と再建(つなぎ方)
胃がんの手術では、がんの場所や広がりに応じて、胃をどの程度切除するかが決まります。主な術式には以下の3つがあります。
幽門側胃切除術(ゆうもんそくいせつじょじゅつ)
胃の出口側(十二指腸側)を2/3から4/5ほど切除する方法です。胃がんの中で最も多く行われる術式です。
胃の入り口(噴門)が残るため、術後の食事の貯留機能が一部維持されやすいのが特徴です。
胃全摘術(いぜんてきじゅつ)
がんが胃の上部にある場合や、広範囲に広がっている場合に、胃をすべて取り除く方法です。
胃が完全になくなるため、食道と小腸を直接つなぎます。
噴門側胃切除術(ふんもんそくいせつじょじゅつ)
胃の入り口(食道側)を一部切除する方法です。
早期の胃がんで、出口側の機能を残せると判断された場合に選択されます。
胃を切ったあとは、必ず「再建(さいけん)」というつなぎ合わせの作業を行います。
例えば、幽門側胃切除のあとは、残った胃と十二指腸をつなぐ「ビルロートⅠ法」や、小腸をつなぐ「ビルロートⅡ法」「ルーワイ法」など、複数のつなぎ方があります。
どの方法を選択するかは、患者様の体のつくりや逆流などの合併症をいかに防ぐかを考慮し、外科医が最も良いと判断したものを選びます。
腹腔鏡手術とロボット支援下手術
かつての胃がん手術は、おなかを大きく20センチほど切る「開腹(かいふく)手術」が一般的でした。
しかし現在では、小さな穴を数箇所開けるだけで済む「低侵襲(ていしんしゅう)手術」が広く普及しています。
腹腔鏡(ふくくうきょう)手術
おなかに開けた小さな穴から、細長いカメラと手術器具を挿入して行います。
モニターに映し出される拡大された画像を見ながら、緻密な操作を行います。
開腹手術に比べて傷跡が小さく、術後の痛みが少ないため、回復が早いという大きなメリットがあります。
ロボット支援下手術(ダビンチなど)
腹腔鏡手術をさらに進化させたものです。
医師が操作台に座り、高精度の3Dカメラで見ながら、人間の手以上の可動域を持つロボットアームを操ります。
手ぶれが完全に除去され、狭いおなかの中でも非常に細かな血管やリンパ節の処理が可能となります。
現在、日本の多くの病院で導入が進んでおり、特に複雑なリンパ節郭清を必要とする症例でその威力を発揮します。
もちろん、すべての方がこれらの最新技術に適応するわけではありません。
がんの進行度や、過去の手術歴、全身の状態によっては、確実性を優先して開腹手術が選ばれることもあります。
どの方法であっても、最終的な目的である「がんを取り切る」ことに変わりはありません。
手術に向けた準備(プレハビリテーション)

最近の医療現場では、手術によって起こりやすい体力・筋力の低下をできるだけ防ぎ、手術後の回復を早めるために、入院前から準備を始める考え方を重視しています。
これは「プレハビリテーション」と呼ばれます。
手術をただ待つのではなく、自ら体を整えることが、合併症の予防に直結します。
口腔ケアの重要性
一見、胃の手術とは無関係に思える「お口のケア」が、実は術後のトラブルを防ぐ鍵となります。
手術中は全身麻酔をかけ、口から肺に管を通します。このとき、お口の中に細菌が多いと、その菌が肺に入り込み、術後に「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」を引き起こすリスクが高まるのです。
入院前から歯科を受診し、歯石の除去や虫歯の治療、正しいブラッシングの指導を受けることが、命に関わることもある肺炎の予防につながります。
多くの病院では、歯科医師や歯科衛生士と連携したチーム医療が行われています。
体力維持と禁煙の取り組み
手術という大きなイベントを乗り切るには、相応の体力が必要です。
無理な運動は必要ありませんが、1日15分から30分程度の散歩を継続し、足腰の筋力を維持しておくことで、術後の立ち上がりや歩行訓練がスムーズに進みます。
術後すぐに動くことは、腸の動きを良くし、血栓(血の固まり)ができるのを防ぐために極めて重要です。
また、もし喫煙されている場合は、今すぐに「禁煙」することが絶対に必要です。
タバコは肺の機能を低下させ、術後の痰(たん)を出しにくくします。また、血管を収縮させるため、手術でつなぎ合わせた部分(吻合部)の治りを悪くし、傷口がくっつかない「縫合不全(ほうごうふぜん)」の原因にもなります。
少なくとも手術の4週間前から禁煙することで、これらのリスクを有意に下げることができます。
今すぐ見る
手術に伴うリスクと合併症への対応

どんなに優れた医師が最新の機器を使って手術を行っても、合併症のリスクをゼロにすることはできません。
しかし、どのようなリスクがあるかを事前に知り、病院側がどのような対策をとっているかを理解しておくことは、不安を和らげる一助となります。
合併症の種類と予防策
胃がん手術に特有の主な合併症には、以下のようなものがあります。
縫合不全(ほうごうふぜん)
胃や腸をつなぎ合わせた部分が、うまくくっつかず、内容物が漏れてしまう状態です。
起こる頻度はそれほど高くありませんが、発生した場合は食事を一時中断し、点滴による栄養管理や、ドレーンと呼ばれる管での排液が必要になります。
膵液漏(すいえきろう)
胃の裏側にある膵臓(すいぞう)の周囲のリンパ節を取り除く際、膵臓が刺激されて膵液という強力な消化液が漏れ出してしまうことです。
周囲の組織を傷つける可能性があるため、細心の注意を払って手術が行われ、術後も管から出る液の性質を毎日チェックします。
腹腔内膿瘍(ふくくうないのうよう)
おなかの中に細菌が繁殖し、膿(うみ)がたまってしまうことです。
発熱や腹痛が生じますが、抗生物質の使用や排液処置によって治療します。
これらの合併症を防ぐため、手術中には徹底した止血と洗浄が行われ、術後も看護師や医師が頻繁にバイタルサイン(血圧や脈拍)や腹部の状態を観察します。
痛みや不安への対応
「術後の痛み」は患者様が最も恐れることの一つでしょう。
現代の外科診療では、痛みを我慢させることはありません。むしろ、痛みをしっかり取ることで深く呼吸ができ、早期の離床(歩くこと)が可能になり、結果として回復を早めるという考え方が主流です。
「硬膜外麻酔(こうまくがいますい)」という背中からの持続的な痛み止めや、点滴による鎮痛薬、あるいは患者様自身がボタンを押して薬を追加できる装置など、何段階もの痛み対策が用意されています。
また、心の不安に対しても、看護師や臨床心理士、あるいは同じ経験を持つ方々(患者会)などの支援を受けることが可能です。
一人で抱え込まず、どんなに小さなことでもスタッフに相談してください。
手術後の生活と注意点

無事に手術が終わり、退院したあとの生活が、患者様にとっての「新しい日常」の始まりです。
胃の一部または全部を失うことで、体には大きな変化が起こります。
術後の食事とダンピング症候群
胃の役割は、単に食べ物を消化するだけでなく、一時的に「貯めておく」ことにあります。
手術によってその貯留機能が失われると、食べたものが急速に小腸へ流れ込み、さまざまな不調を引き起こします。
これを「ダンピング症候群」と呼びます。
早期ダンピング症候群(食後30分以内)
腹痛、吐き気、動悸、冷や汗などが現れます。
小腸に急激に食べ物が入ることで、血管内の水分が腸へ移動し、血圧が変化することなどが原因です。
後期ダンピング症候群(食後2~3時間後)
糖分が急激に吸収されることでインスリンが過剰に出てしまい、逆に低血糖状態になることです。
頭痛やだるさ、震えなどが起こります。
これらを防ぐ最大のコツは、「よく噛んで、ゆっくり食べる」ことです。
一口を小さくし、1回の食事を20~30分かけて楽しむようにしましょう。
また、1日3回の食事では足りない分を、「間食」として回数を分けて摂取する(分食)ことも非常に有効です。
体重の変化と定期検査の継続
術後、ほとんどの患者様が体重の減少を経験します。
これは胃が小さくなったことによる食事量の低下だけでなく、消化酵素の分泌が変わることで、栄養の吸収効率が一時的に落ちるためです。
多くの場合は、半年から1年ほどかけて体が新しい状態に慣れ、体重の減少も止まります。
大切なのは、「体重が減って当たり前」と構え、無理に食べようとして自分を追い込まないことです。
高タンパク・高エネルギーの食事を少しずつ摂り、栄養剤なども上手に活用しましょう。
また、手術でがんを取り除いたあとも、再発や転移の有無を確認するための定期検査は欠かせません。
数ヶ月に一度の血液検査(腫瘍マーカーの確認)や、CT検査、残った胃の内視鏡検査などを継続します。
この期間は、医師や看護師との二人三脚の期間でもあります。
気になる症状があれば「次の外来まで待とう」とせず、早めに医療機関へ相談する習慣をつけましょう。
資料を請求する ▶ 詳しくはこちら
さいごに
胃がんの手術は、人生における大きな試練かもしれません。
しかし、それは決して絶望の始まりではなく、より長く、より質の高い生活を送るための「再出発」のプロセスです。
手術室の扉をくぐるのはお一人かもしれませんが、その背後には執刀医、麻酔科医、看護師、薬剤師、管理栄養士、そして何よりあなたを支えるご家族という大きなチームがついています。
現代の医療が持つすべての力を集結させ、あなたの回復を全力でサポートする準備ができています。
手術後の体は、以前とは少し違う感覚になるかもしれません。しかし、ゆっくりと時間をかければ、体は必ず新しい環境に適応していきます。
再び美味しいものを味わい、家族と笑い合い、趣味を楽しむ日々は、この手術の先にしっかりと続いています。
このコラムが、皆様の不安を少しでも安心へと変え、前向きな気持ちで治療に向き合うための一助となることを願ってやみません。