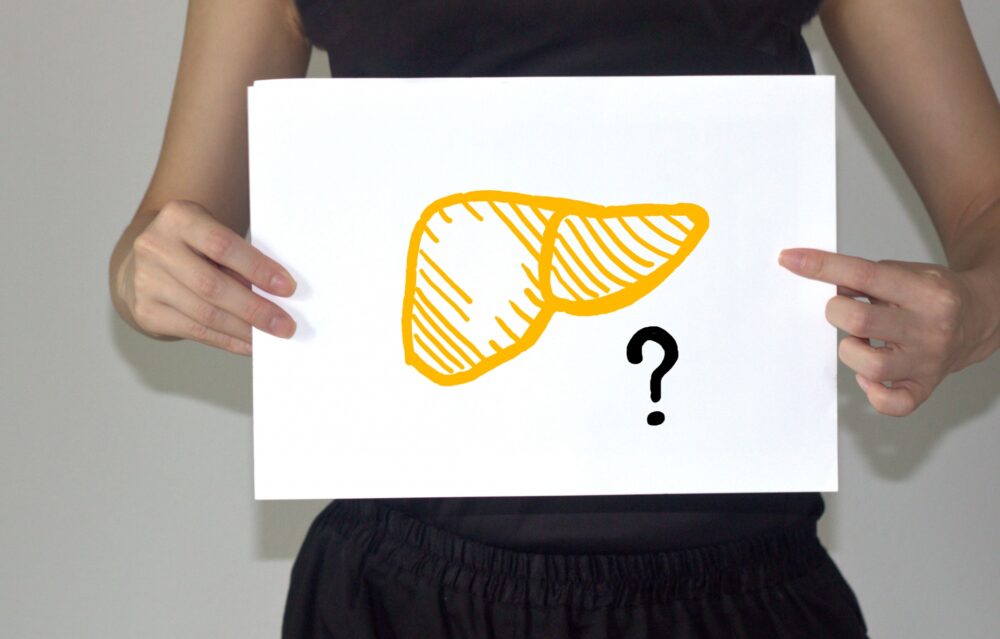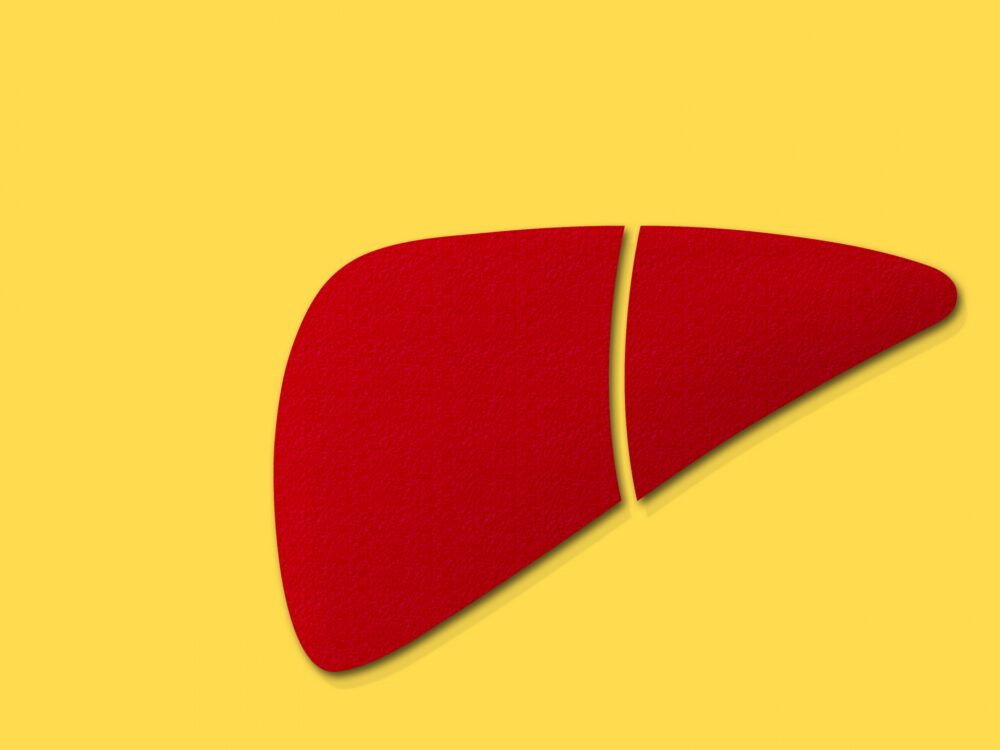肝臓がんの疑いと言われたら?検査方法と診断の流れを解説
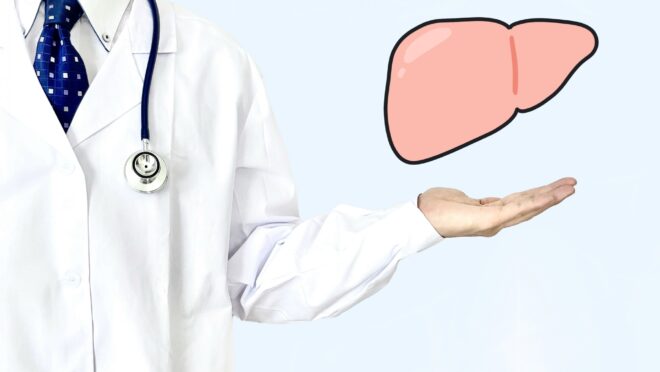
肝臓がんは「沈黙の臓器」とも呼ばれ、早期にはほとんど症状が現れません。そのため、肝臓がんの早期発見には定期的な検査が極めて重要となります。
特にB型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスの感染歴がある方、もしくは肝硬変と診断された患者は肝臓がんの高危険群です。
肝炎ウイルスによる慢性的な炎症や線維化が進行すると、肝細胞がんの発生リスクが高くなります。
近年、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)による肝硬変や肝がんも増加傾向にあります。
このコラムでは、肝臓がんの検査方法や診断の流れについて、血液検査や腫瘍マーカー(AFP、PIVKA-IIなど)の測定、超音波(エコー)、造影CTやMRIによる画像診断、組織生検による病理検査までを詳しく取り上げ、多くの方が抱える疑問や不安を解消する案内となることを目指します。
肝臓がんの代表的な検査

肝臓がんの早期発見には、定期的な検査が欠かせません。
しかし、検査と一口に言っても、その目的や得られる情報はさまざまです。
肝臓は前述したように「沈黙の臓器」と呼ばれるほど症状が出にくく、気づいたときには病気が進行していることも少なくありません。
そのため、画像検査や血液検査を組み合わせて、できるだけ早い段階で異常を捉えることが重要になります。
ここでは、肝臓がんの診断に用いられる代表的な検査について、それぞれの特徴や役割をわかりやすく紹介していきます。
超音波(エコー)検査
超音波検査(エコー)は、肝臓がん検査の中でも最も広く行われている方法です。
体表からプローブを肝臓部位に当て、音波の反射を利用して臓器内部の様子を画像化します。
被ばくがなく、短時間で繰り返し利用可能なため、肝硬変や肝炎ウイルス感染者の定期サーベイランスとして定着しています。
肝臓腫瘍が存在する場合、腫瘍の大きさ、形、個数、血管との関係、腹水の有無などが観察されます。
最近では、造影剤を注射して腫瘍の特徴を明確にする造影超音波検査も普及しています。
これにより小さな病変や血流異常も検出しやすくなり、早期の肝細胞がん発見に有効です。
肥満や体内深部に腫瘍が分布する場合は観察精度が低下するため、他の画像診断と併用して評価します。
CT・MRI検査
造影CTおよびMRIは、肝臓内腫瘍を詳細に観察し、その種類や広がり、進行度を評価する画像診断法です。
造影CT検査
X線と造影剤を使用し、腫瘍の位置・大きさ・内部構造、肝動脈や門脈など血管との関係、周囲臓器への転移有無も確認可能。
造影パターンの違いから、良性と悪性の判別にも役立ちます。
MRI検査
磁場と電波を利用するため被ばくはありません。
微細な肝腫瘍や血管・胆道との関係を高分解能で描出でき、特に造影剤(ガドリニウム系)を用いると診断能が格段に向上します。
造影CTで検出が難しい場合にも有用です。
CTやMRIは、肝臓がんの発見・分類、治療方針決定や手術適応判定などに欠かせない検査方法です。
血液検査と腫瘍マーカー
血液検査では、肝機能を評価するAST、ALT、ALP、γ-GTP、ビリルビン値、プロトロンビン時間などに加え、腫瘍マーカー測定が肝臓がん診療の大きな柱となります。
AFP(アルファ・フェトプロテイン)
肝細胞がんや胎児性腫瘍で特異的に上昇。数値が高い場合、肝がんの疑いが強まります。
PIVKA-II(異常プロトロンビン)
肝細胞がんで産生されるタンパク質で、値が高い場合は悪性度が高い腫瘍を示唆します。
AFP-L3分画
AFPの中でも肝細胞がんに特異的な分画を検出します。
腫瘍マーカーが2種類以上同時に上昇していれば、がん存在の可能性がより高まります。
ただし、肝炎や肝硬変、他の腫瘍でも上昇するため、画像診断や病理検査と組み合わせて総合的な判断が必要です。
肝臓がんの診断の流れ

経過観察が必要な患者とは
慢性肝炎や肝硬変のある肝臓がん高危険群の患者は、定期的な診療と肝臓の経過観察が必要です。初期の段階で発見されるほど、治療の選択肢が広がります。
診療ガイドラインでは、以下のような頻度での経過観察が推奨されています。
超高危険群(肝硬変)
→ 3~4か月ごとに腹部超音波(エコー)検査+腫瘍マーカー(AFP・PIVKA-II)測定
高危険群(慢性肝炎や非ウイルス性肝硬変)
→ 6か月ごとに同様の検査
血液検査やエコーで異常が見つかった場合は、CTやMRIなどでさらに精密な評価が実施されます。
病期(ステージ)の判断
肝臓がんの進行度(ステージ)は、腫瘍の個数・大きさ・分布・血管侵襲・転移の有無・肝機能などの組み合わせで決まります。
CTやMRIによる画像診断と、必要に応じて組織生検結果なども踏まえ下記のような点を確認し、総合的に評価します。
・腫瘍の大きさ・個数・位置
・血管(門脈、肝動脈)への浸潤や閉塞の有無
・腹水の有無や、他臓器への転移
・肝機能評価(Child-Pugh分類など)
診断が出たら
診断結果が得られたら、主治医から患者とその家族へと病状の説明が行われたうえで、今後の治療方針を決定します。
肝臓がんは状態や進行度によって
・外科手術
・ラジオ波焼灼(RFA)やマイクロ波治療
・カテーテルを使った血管内治療(肝動脈化学塞栓療法:TACE)
・放射線治療
・分子標的薬などの内科治療
といったさまざまな治療選択肢があります。
適応される治療は、腫瘍の性質や分布、肝機能や全身状態によってそれぞれ異なります。
主治医と十分に相談し、納得のいく方針を話し合いながら選択しましょう。
肝臓がんにおける最新の検査とは

肝臓がんの診断は年々進歩しており、従来の検査だけでは捉えきれなかった情報を補うための新しい技術が次々と実用化されています。
特に画像診断の分野では、遠隔で行える超音波検査や、がんの活動性をより詳しく評価できるPET検査など、より精度の高い方法が登場しています。
また、血液検査でも新たな腫瘍マーカーやゲノム解析が導入され、がんの特徴をより深く理解することが可能になってきました。
ここでは、こうした最新の検査技術がどのように肝臓がんの診断に役立つのか、そのポイントをわかりやすく紹介していきます。
新しい画像診断
肝臓がんの画像診断は、従来の検査では見つけにくかった小さな病変や早期がんを捉えるため、さまざまな最先端技術が導入されています。
造影超音波検査は、造影剤を使うことで血流の変化を詳しく観察でき、微細な病変の検出力が大きく向上しています。
マルチスライスCTでは、肝臓全体を細かい断面として立体的に描き出すことができ、腫瘍の位置や広がりをより正確に把握できます。
さらに、最新のMRI技術(Gd-EOB-DTPA造影)は、肝細胞に特異的に取り込まれる造影剤を使用するため、微小な悪性腫瘍でも高い精度で描出できる点が特徴です。
加えて、PET-CTはがん細胞の代謝活動を可視化でき、特に転移の有無を調べる際に有用とされています。
これらの技術を組み合わせることで、より小さな腫瘍も見逃しにくくなり、早期診断の可能性が大きく広がっています。
血液検査と腫瘍マーカーの進化
従来から使われてきた腫瘍マーカーであるAFPやPIVKA-IIに加えて、AFP-L3分画やDCPといった、より精度の高い指標が臨床の場で活用されるようになっています。これらは腫瘍の性質や進行度をより細かく把握する助けとなり、診断の確度向上に貢献しています。
さらに近年は、ゲノム解析技術の発展によって、血液中から腫瘍に関連する遺伝子情報を読み取る研究が加速しています。
マイクロRNAや遺伝子変異、エクソソームといった微細な分子を手がかりに、がんの存在や特徴をより早い段階で捉えようとする試みが進んでいます。こうした新規マーカーはまだ研究段階のものも多いものの、将来的にはより正確で個別化された診断につながる可能性が高いと考えられています。
また、血液だけでがんの情報を得る「リキッドバイオプシー(液体生検)」も注目を集めています。体への負担が少なく、繰り返し検査しやすいという利点があり、早期発見や治療効果のモニタリングに役立つ技術として期待されています。
これらの進化により、血液検査は今後ますます肝臓がん診断の中心的な役割を担っていくと考えられています。
肝臓がんの検査Q&A

検査はどのくらいの頻度で受けるべき?
肝臓がんは、肝炎ウイルス感染や肝硬変などの基礎疾患がある人ほど発症リスクが高く、定期的な経過観察が極めて重要です。
特に、肝硬変やB型・C型肝炎でウイルス量が高い場合などの「超高危険群」では 3〜4か月ごと、それ以外の「高危険群」では 半年ごとの検査が推奨されます。
基本となるのは 腹部超音波検査と腫瘍マーカー(AFP、PIVKA-IIなど)の組み合わせです。これにより、症状が出にくい早期の段階でも異常を捉えやすくなります。
病状や肝臓の状態によっては、主治医の判断で CT、MRI、造影超音波、血管造影 などの精密検査が追加されることもあります。
自分がどのリスク群に該当するかを医師と共有し、適切な検査間隔を保つことが大切です。
検査結果が出るまでの時間は?
検査の種類によって結果が出るまでの時間は大きく異なります。
血液検査や腹部超音波検査は、施設によっては当日中に結果がわかることも多く、遅くても数日以内に確認できます。
一方、CTやMRIなどの画像診断については、撮影自体は30分前後で終わります。しかし、専門医による読影(画像の解析)に時間を要するため、結果が出るまで 数日〜1週間程度かかることがあります。
さらに、腫瘍の確定診断に用いられる 組織生検(病理検査) は、細胞の染色や詳細な解析が必要なため、一般的に数日から2週間程度を要します。
検査に伴うリスクや副作用は?
肝臓がんの検査は多くが安全に行えるものですが、それぞれに特徴があります。
超音波検査やMRIは放射線を使用しないため、身体への負担が少なく、繰り返し行っても問題ありません。特にMRIは造影剤を使わない撮影方法もあり、腎機能に不安がある人でも実施しやすい検査です。
一方、CT検査はX線を使用するため一定の被ばくがあります。また、造影剤を使用する場合は、まれにアレルギー反応や腎機能への影響が生じることがあります。
組織生検は、針を刺して組織を採取するため、わずかですが出血や感染のリスクがあります。ただし、医師が超音波などで位置を確認しながら慎重に行うため、重大な合併症が起こることはまれです。
造影剤を使う検査を受ける際は、腎機能障害の有無、アレルギー歴、服薬状況を事前に医療スタッフへ伝えるようにしましょう。
資料を請求する ▶ 詳しくはこちら
おわりに
肝臓がんは早期発見が患者の将来に大きく影響します。最新の医療技術・検査法の進歩により、肝臓がんの診断精度は年々向上していますが、何よりも重要なのは「自分が高危険群かどうか」をよく知り、定期的な検査・診療を継続することです。
不安や疑問がある方、検査や治療に関しての案内を受けたい方は、医療機関の相談窓口や専門医に早めにご相談ください。
適切な検査と的確な診断によって、一人ひとりの患者さんがより良い治療と生活を送れるよう、医療チームが全力でサポートします。
自身の健康と未来のため、積極的な行動を今日から始めましょう。